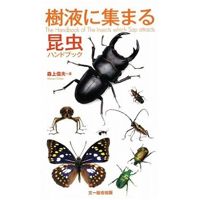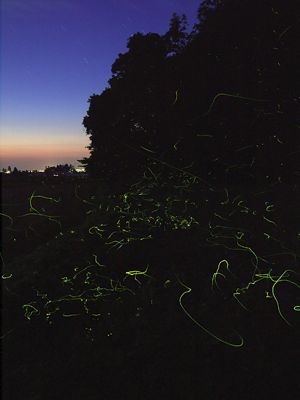アブラゼミの羽化はとっても時間がかかる!
子供の観察にいいとは言われるが、いきなり相当な辛抱を強いられて、
子供のやる気がそがれはしないかと心配になったりする。
最初のステップからして大変だから。
18時半ともなると幼虫は地面を歩いたり、木を登り始めている。
意外に早い。

気に入った場所にとまるとジッとして動かなくなる。
でも、いよいよ羽化のスタートだ・・・なんてわけにはいかない。
大変なのはここからだ。
左の写真から、右のわずかに背中に割れ目が入る瞬間までは約1時間!
あまり数の少ない観察の中でのことだが(20回もないと思う)、
必ずこれくらい待たされているように思う。
羽化が近づくと、お腹が波打つような運動が始まる。
すると、お腹の節間が広がってきて、全体の形も変わってくる。
これが始まったら5分と経たずに羽化が始まるのだが、その後も長い


でも背中が割れて翅が伸びきるまでも1時間だ。
最初の何の変化もない1時間にくらべれば、ぶら下がって休止する20分など大したことはないだろう。

頑張って観察をやり遂げた子供は、よく褒めてあげてください。
観察はもう懲り懲りなんて思ってしまわないように。