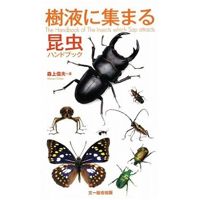この虫にはだいぶ前にも一度あっています。2000年9月、帰省先の山形からの帰りに見て、その時はクダマキモドキと間違えてしまいました。不覚にもその間違いに気づいたのは昨年になってからのことです。ヘリグロツユムシという存在を意識したのもそれからで、今年になってようやくまとまった数を見ています。
-
ナギサスズ
ウミコオロギ(ナギサスズ)は鳴かないので、声をたよりに探すわけにはいかない。でも、丸い石がごろごろしているような海岸にすむと何かに書いてあった。その情報を頼りに、庄内の海岸を探してみた。
すると昨年から何度も通った場所がまさにそうだったことに今さら気づく。漂流物をどけて探しはじめると、すぐにそれらしい姿が目に飛び込んできた。
拍子抜けするほど簡単に見つかったが、それからが一苦労だった。
丸い石の層はかなり深く、石をどけても更に下に隠れてしまう。延々その繰り返しなのだ。。。
10分ほどかけてようやく雌雄満足のいくカットが撮れた。しかし、これは成虫なんだろうか。
親になっても翅をもたないので、はっきりわからない。
体型のバランスを見ると、たぶん成虫なのだろう。 -
クマゼミ
ようやくこの耳でクマゼミの声を聞き、この目で姿を見ることができた。いつか見られると思ってばかりで自分から動かなかったのはいけなかった。ずいぶん時間がかかってしまったが、これでようやくホッとできた。
急に思い立って鶴岡から車を走らせ伊丹まで。
2日の朝に出て、途中、能生のヒメハルゼミの声を聞き、伊丹に入ったのは3日の朝。1日かかってしまった。
ずっと天気が悪い中走ってきたが、伊丹は真夏の日差しでクマゼミの大合唱が迎えてくれた。伊丹に行ったのは、伊丹市昆虫館の学芸員、奥山さんに前から予告していたからだった。(でも、当日朝になって突然電話してしまったりして本当に申し訳ありませんでした。。。)
昆虫館のある昆陽池公園は、確かにクマゼミの声で一杯だった。

雄のクマゼミ。右は鳴いている姿。翅をやや開いて、お腹を激しく動かしている。


センダンだろうか?
クマゼミが大量に集まっている木があった。


話に聞く通り、クマゼミは午前中メインで鳴いていた。
午後も鳴いているものはいたが少数。
午後といえば、君らいたのかという感じにアブラゼミとニイニイゼミが鳴き争っていた。 -
ミドリグンバイウンカ
滋賀のサービスエリアにて見たこともないウンカに出会った。
クチナシの葉にいた緑色の小さなウンカ。拡大撮影したらとっても魅力的な虫と気づいた。
ミドリグンバイウンカ。名前を見るのも初めてだ。右は幼虫。


こんな光沢のある葉にダイレクトにライトを当ててはNGだった。。。

同じSAにて、イタドリの葉に群れていたのはアオドウガネか。
小諸でも山形でも見たことのない甲虫だ。

見た瞬間に、いつものオオニジュウヤホシと違うように思った。
ニジュウヤホシテントウも山形では見られない甲虫である。

西日本に行った経験は片手で数えるほどしかない。しかも夏は初めてだ。
ちょっと車をとめて見てまわると、私には見知らぬ連中が色々いて驚かされる。
今回、滞在時間が極端に短かかったのはやっぱり残念だった。 -
ハイイロゲンゴロウ
ハイイロゲンゴロウを初めて見たのは30才くらい、小諸でのことだ。
子供の頃に見た図鑑には、ごく普通種的な書き方がされていて、何だか悔しい思いをしていた。小学生の頃に田植えの頃にはよく水棲昆虫さがしをやっていたが、その頃とれたのはヒメゲンゴロウ、コシマゲンゴロウ、マルガタゲンゴロウ、それとマメゲンゴロウ数種くらいで、寂しいものだった。ハイイロゲンゴロウは憧れの虫の1つだったのだ。
小諸でも春はとれなかった。真夏にだけ、気がつくと休耕田にたくさん泳いでいるのを見るという感じ。夏の庄内にも少なからずやってくるようで、これまでにもう何回か見ている。昨年は飛島の海岸で見たりして、あれは驚いた。


ハイイロゲンゴロウはよく飛ぶ。水面からも飛び立つそうだが、確かにスキあればすぐに飛んで逃げられてしまう。水槽での撮影中たまたま写った下の写真。こんな瞬間からもその様子はうかがえる。
翅って水中でも開けるものなんだ?肉眼では何だか翅をばたつかせているだけにしか見えなかった。思いっきりピンぼけだが、ピントのあった写真が撮れるまで捨てずに残しておこう。

-
アブラゼミの羽化
アブラゼミの羽化はとっても時間がかかる!
子供の観察にいいとは言われるが、いきなり相当な辛抱を強いられて、
子供のやる気がそがれはしないかと心配になったりする。
最初のステップからして大変だから。18時半ともなると幼虫は地面を歩いたり、木を登り始めている。
意外に早い。

気に入った場所にとまるとジッとして動かなくなる。
でも、いよいよ羽化のスタートだ・・・なんてわけにはいかない。
大変なのはここからだ。左の写真から、右のわずかに背中に割れ目が入る瞬間までは約1時間!
あまり数の少ない観察の中でのことだが(20回もないと思う)、
必ずこれくらい待たされているように思う。
羽化が近づくと、お腹が波打つような運動が始まる。
すると、お腹の節間が広がってきて、全体の形も変わってくる。
これが始まったら5分と経たずに羽化が始まるのだが、その後も長い


でも背中が割れて翅が伸びきるまでも1時間だ。
最初の何の変化もない1時間にくらべれば、ぶら下がって休止する20分など大したことはないだろう。

頑張って観察をやり遂げた子供は、よく褒めてあげてください。
観察はもう懲り懲りなんて思ってしまわないように。 -
ヒメハルゼミ
ちょっと遠出して、能生のヒメハルゼミの生息地を訪れた。
能生のヒメハルゼミの生息地は白山神社の裏山。
ここは日本海側の北限とされ国指定天然記念物に指定されている。

実は、ヒメハルゼミの声はまだこの耳に聞いたことがない。
蝉時雨と表現されるいっせいに合唱する様子を、録音されたものを聞いた事があるが、何だかよくわからなった。
森に入ってすぐに聞こえてきたのはニイニイゼミ。
日が差してくると明らかに別の声が聞こえてきて、やがてものすごいボリュームの大合唱となった。
(鳴き声は音集めで)

高い木の上で鳴いているのでセミの姿が見えない。
一度だけ、ビデオを撮るチャンスに恵まれたが、写真の方は満足のいくものが撮れなかった。
↓こちらはビデオ映像
-
アオバハゴロモ幼虫
庭のムクゲに気がついたらアオバハゴロモの幼虫がたくさんついていて、
枝がところどころ真っ白くなっている。
白い毛のようなものは、幼虫の出すロウ物質・・・(→かがくナビにも記事を書きました)ムクゲに接して生えているハギには、ベッコウハゴロモの幼虫がいた。
こちらも、お腹の先から毛束のようなロウ物質を出して、何とも怪しげな姿をしている。

ロウ物質の束は、傘のようにすぼめたり開いたりできる。
指を近づけたりしておどかすと、毛束をクジャクの羽のように大きく開いて、
その下に身を隠そうとする。タンポポなどの綿毛の種か、カビなのか、いったい何に似せているつもりなのだろう。
いずれにしても、正体が虫だとはなかなか気づきにくいだろう。 -
ヤマトマダラバッタの幼虫
昨日の撮影では物足りないような気がして、再び砂浜を訪れた。
ところが、今日は朝から気温が上がって砂が熱いらしい。
ヤマトマダラバッタ(ヤマトバッタ)の幼虫は砂地を嫌がって、葉の上などに避難しようとする。
時々日がかげったところを狙って、いくつか追加撮影。この幼虫は、もっとも成長しているもので、1cmを超えていた。
茶色い背中で擬態は今ひとつかと思ったのだが、写真に撮ったらナカナカよく
周りにとけ込んでくれた。

こちらは、やや若い幼虫。
彼らはやや突きだした複眼でもって自分の姿を見ることができるのだろうか。
自分の姿を客観視できなければ、砂地でジッと動かない事のメリットにも気がつけない
と思うのだが、どうだろう。