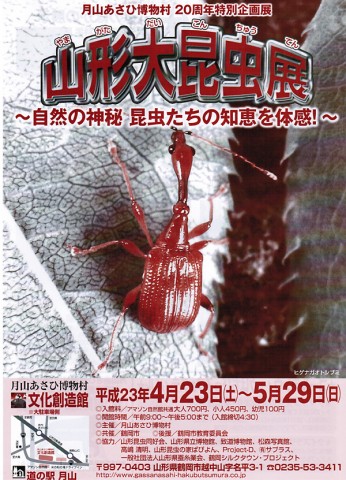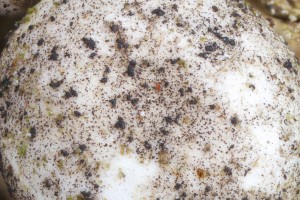山形新聞で連載中の「やまがた昆虫図鑑」。
おかげさまで好評をいただき、まもなく200回に届こうとしております。
その中で、私は1つ大きなミスをやっていたことに最近気づきました。
4月7日づけのニホンセセリモドキですが、ヘアペンシルを出しているのは「雌」として書いています。
これが大きな間違いで、私はもうしばらく勘違いしながら、この虫を観察しておりました。
正しくは「雄」です。
多くのガが雌が性フェロモンを発する行動と同じように見てしまっていました。
新聞紙面では訂正を入れることができませんので、まず、ここで訂正させていただきます。
もちろん、書籍版の発刊の際には、正しく修正したものをお届けします。