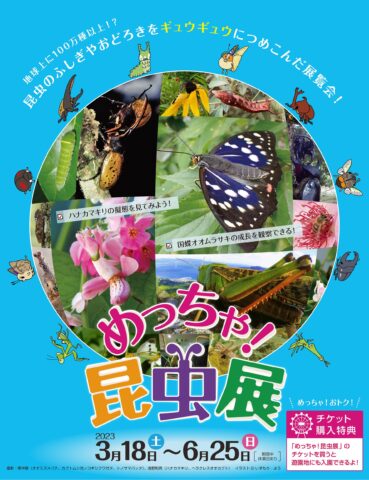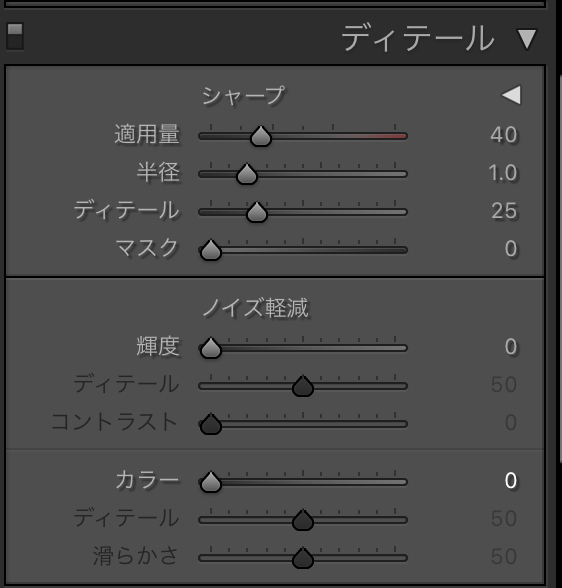もう10年前になってしまいますが、数年に渡って、Photron社の高速度カメラFASTCAMシリーズをお借りする機会に恵まれました。飛翔をはじめ、昆虫の行動を様々撮影しました。当時は、Photron社へのデータ提供が主な目的でしたし、YouTubeに映像を出す事にまだまだ慎重・・・というか流用されるとか事故を恐れ一部のみの公開に留めましたが、今思えばただの出し惜しみ、トータルでもったいないことでした。年を重ねて余計その思いが強まります。
念願かない、現在では自分持ちの高速度カメラChronos2.1を手にしていますが、スペック的には10年以上も前のFASTCAMシリーズに劣る部分も多いです。ここに紹介するPhotron FASTCAMの動画は、まだまだ見応え十分。とても10年以上前の撮影とは思えません。
フォトロンFASTCAMは進化を続けていて、現在は4K1250fpsの機種をはじめ大変魅力的なラインアップ。 https://www.photron.co.jp/products/hsvcam/